「指しゃぶりはいつまでして良いんだろう」
「歯への影響が心配」
「やめさせた方が良いのかな?」
指しゃぶりをする子をもつ親なら、一度は心配したことがあるのではないでしょうか。
本記事では、子どもが指しゃぶりをする理由や、歯への影響、いつまでにやめたら良いのかを解説していきます。
指しゃぶりはなぜおこる?

子どもが指しゃぶりをするのにも、様々な理由があります。
その主な理由がこちらです。
- 生まれつきの本能(吸啜反射)
- 安心感を得るため
- ストレスの解消
- 習慣になっている
- 寝る前のルーティンに
生まれつきの本能(吸啜反射)
赤ちゃんは生まれつき吸啜(きゅうてつ)反射という本能をもっています。
母乳やミルクを吸うための自然な行動のため、1歳までの指しゃぶりは心配する必要はありません。
安心感を得るため
指しゃぶりは子どもにとって気持ちを落ち着かせる方法の一つです。
寝る前や、不安を感じたときに指をしゃぶることで安心感を得ています。
ストレスの解消
環境の変化(引っ越し、入園、家族の変化など)があると、指しゃぶりが増えることがあります。
また、赤ちゃん返りの一環として指しゃぶりが始まることもあります。
習慣になっている
指しゃぶりは繰り返すうちに習慣化し、無意識のうちに指しゃぶりをするようになります。
2〜3歳を過ぎても指を吸っている場合は、習慣として根付いていることが多いです。
寝る前のルーティンになっている
眠たくなると指しゃぶりをする子どもは多いです。
これは、指しゃぶりが入眠のサインになっているためです。
寝るときに指しゃぶりをすることによって安心して眠りにつくことができます。
いつまでにやめたほうが良い?

指しゃぶりをしているのを見ると、いつまで良いのか不安になりますよね。
今回は歯への影響も合わせて年齢順に紹介していきます。
0〜1歳:自然な行動なので無理にやめさせなくて大丈夫!
まだ「吸う」ことが本能的な時期であり、無理にやめさせる必要はありません。
安心感を得る手段のひとつなので、温かく見守りましょう。
2〜3歳:様子を見ながら少しずつ減らしていくのが理想
3歳頃になると、言葉で気持ちを伝えられるようになり、指しゃぶり以外の方法で安心感を得られるようになってきます。
3歳までは歯並びに影響がないと言われていますが、習慣的に指しゃぶりをしている場合は4歳以降も続く可能性があります。
手先を使った遊びに誘うなど、少しずつ指しゃぶりを減らす工夫をしてみましょう。
4〜5歳:歯並びや発音への影響が出る可能性があるので、卒業を目指そう
長期間指しゃぶりをしている場合は、下の動きに影響し、発音がはっきりしなくなることもあります。
指しゃぶりをやめたほうが良い理由を伝えても理解できる年齢なので、子どもが自らやめられるようにサポートしていきましょう。
6歳以降:専門家への相談も視野に
指しゃぶりの習慣が抜けずに吸っている子もいますが、中には精神的な不安やストレスが関係している場合もあります。
指しゃぶりは歯並びに必ず影響するの?

指しゃぶりをしていたら必ず歯並びに影響するわけではありません。
「吸う強さ」や「頻度」によって変わってきます。
筆者には2人の子どもがおり、上の子は5歳、下の子は3歳まで指しゃぶりをしていました。
しかし、出っ歯になったのは下の子だけです。
指しゃぶりの長かった上の子は、歯並びは綺麗なままでした。
しかし、これはほんの一例です。
できるだけ早くゆびしゃぶりを卒業した方が、歯並びに影響は少ないでしょう。
子どもが自らやめられる方法
指しゃぶりは子どもの気持ちの安定につながっていることが多いため、成長に合わせて無理なく卒業することが大切です。
指しゃぶりのやめ方は別記事にまとめました。
詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

まとめ

指しゃぶりは、成長とともに自然にやめていく子もいますが、習慣化したり不安を感じて吸ったりしている子も多いです。
吸い方や期間によっては歯並びなどに影響が出る場合もあります。
3〜5歳頃を目安に、子どもが自分でやめられるようにサポートしていきましょう。

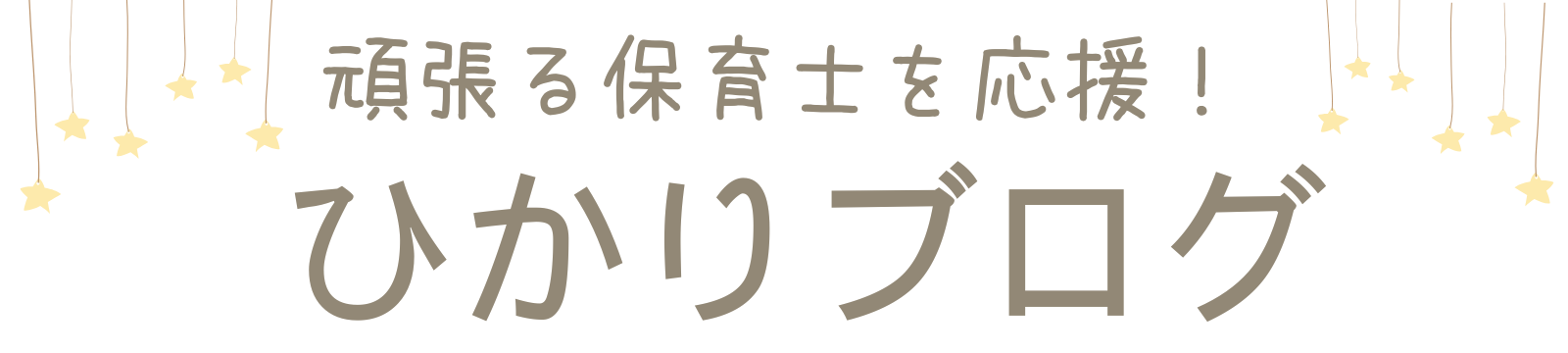

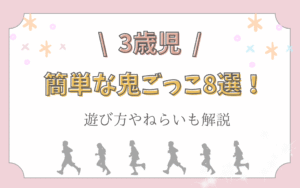
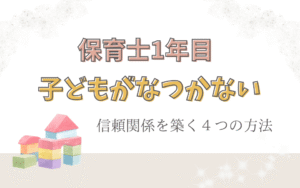



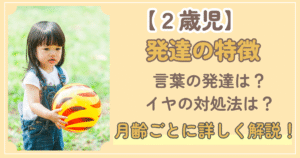
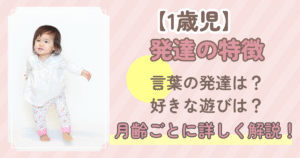
コメント